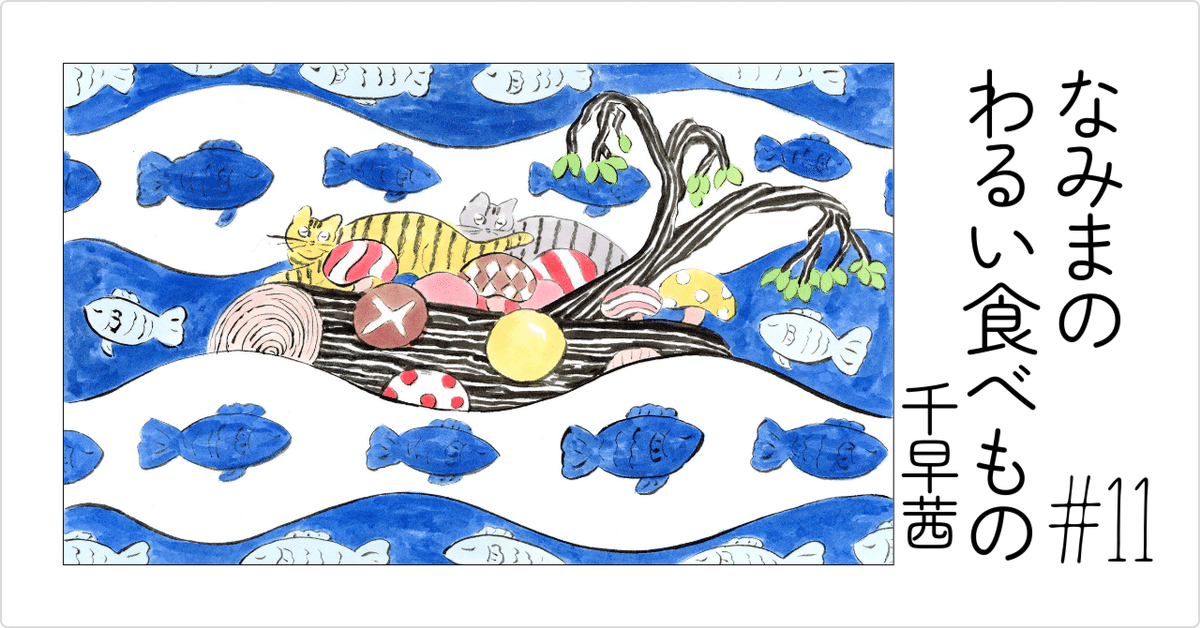
韓国のスプーン 千早茜「なみまの わるい食べもの」#11
[第2・4水曜日更新 はじめから読む]
illustration:北澤平祐
傷痕をめぐる十の短編が入った『グリフィスの傷』という本を刊行した。そのせいか、自らの傷とその経緯を開示してくれる人がちらほら現れるようになった。ありがたく、観察し、聴く。その中で、本をくれた年上の友人もいた。自分の身体の傷痕をあらかた見せてくれたあとで送ってくれたその本は韓国の詩人、キム・ソヨンの『奥歯を噛みしめる 詩がうまれるとき』というエッセイであった。「傷」について書かれているという。
異国のエッセイ。身構えてしまう。異国の小説よりずっと身構える。なぜかというと、経験上、エッセイでは小説より説明や描写を省くからだ。例えば、蕎麦をあむあむ食べてしまう話を書くとき、私は使用するカトラリーが箸であることも、蕎麦とはあむあむするのではなくすするのが推奨される食べものであることもわざわざ説明しない。それらは話のテンポのために省かれる。もし、これを違う文化圏の人にもわかるように事細かに書いたら、日本食の文化を考察する文章になりかねない。そもそも、あむあむといったオノマトペは通じるのだろうか。エッセイは読者との暗黙の了解に依っている部分が大きい、と私は認識している。なので、翻訳の話がきても尻込みしてしまうし、異国のエッセイを読むときも本意を汲み取れているのだろうか、認識違いをしてやいまいか、とはらはらするのだ。
そんなぐずぐずした気持ちで本をひらいたが、「食べるためではなく、遊ぶために料理をすることがある」の一文で前のめりになる。のり巻きやおいなりさん、餃子を作る、とある。のり巻きには「キンパ」、餃子には「マンドゥ」とルビがふってあるが、おいなりさんにはないので、ネットで検索してみたら「ユブチョバプ」という稲荷寿司の油あげの口のほうを上にして具材をたっぷりのせた、カラフルなおいなりさんがでてきた。あ、これは楽しい、と思う。私は水餃子作りを「兵馬俑」と呼ぶが、確かにあれも遊びかもしれない。キム・ソヨンはそこから労働と遊びの違いについて考え、食べものをほおばる感覚について書いていく。ほおばる記憶から亡き父親、そして老いて娘のようになった母親との関係性を描く。
この本で書かれている傷は目に見えるものではない。詩人である著者は見えないものに目を凝らす。嫌いだった母親を介護しながら自身の気持ちや傷に向き合い、ときには「歯をぎりぎりと食いしばりながら」耐える。描かれているのは、そういう表にはでない傷みなのだ。「見方のせいで在るものを無いと言うのは、簡単で愚かなことだ」と書く彼女は、自身の「見る」行為をも疑い、詩を書く。旅したり、友人と散歩したり、新型コロナウイルスに生活を侵食されたりしながら。「詩人が嫌い」と言いながら誠実に詩を書く彼女の矛盾が好きになってくる。
著者が子供の頃、発泡スチロールの箱が家に届き、開けたらおびただしい数の生きたテナガダコが入っていたという話が面白かった。テナガダコたちはうねうねと箱から脱出し、家の中を這いまわる。悪夢のようだ。つかまえて箱に戻そうとするも、蓋を開けると、今度は違う個体が逃げてしまう。著者と妹は熱湯をかけてテナガダコたちの動きを封じるのだが、活きダコが好きな父親は帰宅してがっかりする。韓国では日常の食卓に活きダコがのぼるのかと驚き、大学のときに韓国に行ったことを思いだした。海の近くの市場で、ガイドの方が生ものを禁じたにもかかわらず、私はこっそりタコを食べたのだ。タコは斧のような包丁でぶつ切りにされ、刻んだニラと調味料でさっと和えられた。発泡スチロールの皿の上でタコの身はまだ動いていた。えいやっと口に入れると、コリコリムニムニとし、胡麻油の香りのする甘辛いタレがよくからんでいて美味しかった。あのときの興奮と楽しい気持ちがよみがえった。著者の意図とは離れる読み方かもしれないけれど。
父親が使っていたスプーンの話も印象的だった。父親のスプーンだけは銀製で、毎日、磨かれた。藁に真っ黒な炭をつけてこすり、歯磨き粉をつけた布巾で磨き、最後に乾いた布巾で拭きあげる。鏡のように光る銀色のスプーンを想像した。最初の一口はスプーンで飲むスープ、とあるので、汁物はスプーンを使い、スプーンは毎食使われるカトラリーなのだと知れた。五十年以上使われ、そのたびに磨きあげられた結果、銀のスプーンに穴があく。著者はその穴のあいたスプーンをもらう。
私も韓国のスプーンをひとつ持っている。柄はすっと細長く、すくう部分は浅く、正円に近いくらい丸い。料理人である元夫の持ちものだった。コンロ脇のツールスタンドに他の調理器具と共に入れてあったので、あるとき手に取ってみたらすごく使いやすかった。柄が長いので、すくいやすく、手も汚れにくく、なにより混ぜやすい。餃子の具を練るのも、和えものも、鶏つみれを作るのも、そのスプーンばかりを使っていたら、韓国のものだと教えてくれた。「韓国は混ぜる文化だから。よく考えられているよね」と元夫は言った。
離れることが決まったとき、共有の持ちものはわりとすんなり分けられた。東京で契約した部屋は狭く、私はあまりものを多く持っていく気がなかったからだ。おまけに人生初めてのIHコンロの台所だったので調理器具もほとんど手放した。ただ、「なにか欲しいものはない?」と訊かれたとき、私はまっさきに「あのスプーン」と言った。元夫は「あの」だけで察して、ちょっと困った顔をした。どちらの手にも馴染む、ほんとうに使いやすいスプーンだったのだ。
一人暮らしを経て、違う人と暮らすようになったが、まだスプーンは使っている。磨かないので、傷だらけでくもっていて、銀色というよりは鼠色だ。日常的に使うので、しぶしぶくれた人のことを思いだすことはなかったが、本書を読んでひさしぶりに彼のちょっと困った顔が浮かんだ。

【なみまの わるい食べもの】
毎月第2・4水曜日更新
▼わるい食べもの(千早茜×北澤平祐) - LINE スタンプ | LINE STORE
千早茜(ちはや・あかね)
1979年北海道生まれ。小学生時代の大半をアフリカで過ごす。立命館大学文学部卒業。2008年『魚神』で小説すばる新人賞を受賞しデビュー。同作で09年に泉鏡花文学賞、13年『あとかた』で島清恋愛文学賞、21年『透明な夜の香り』で渡辺淳一文学賞、22年『しろがねの葉』で直木賞を受賞。小説に『赤い月の香り』『マリエ』『グリフィスの傷』など、エッセイ集に『わるい食べもの』『しつこく わるい食べもの』『こりずに わるい食べもの』などがある。
X: @chihacenti

